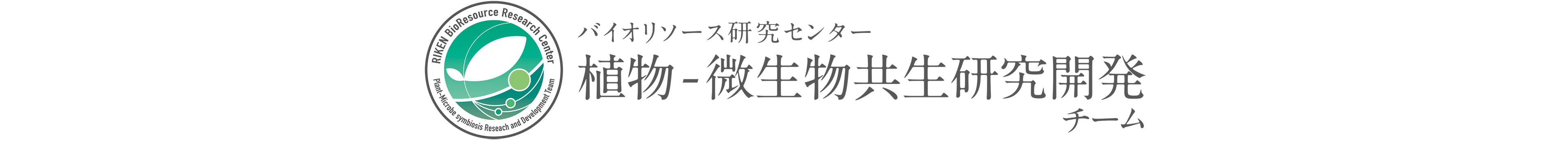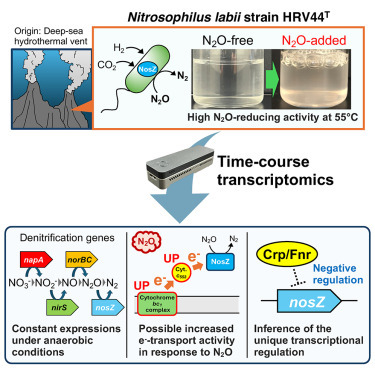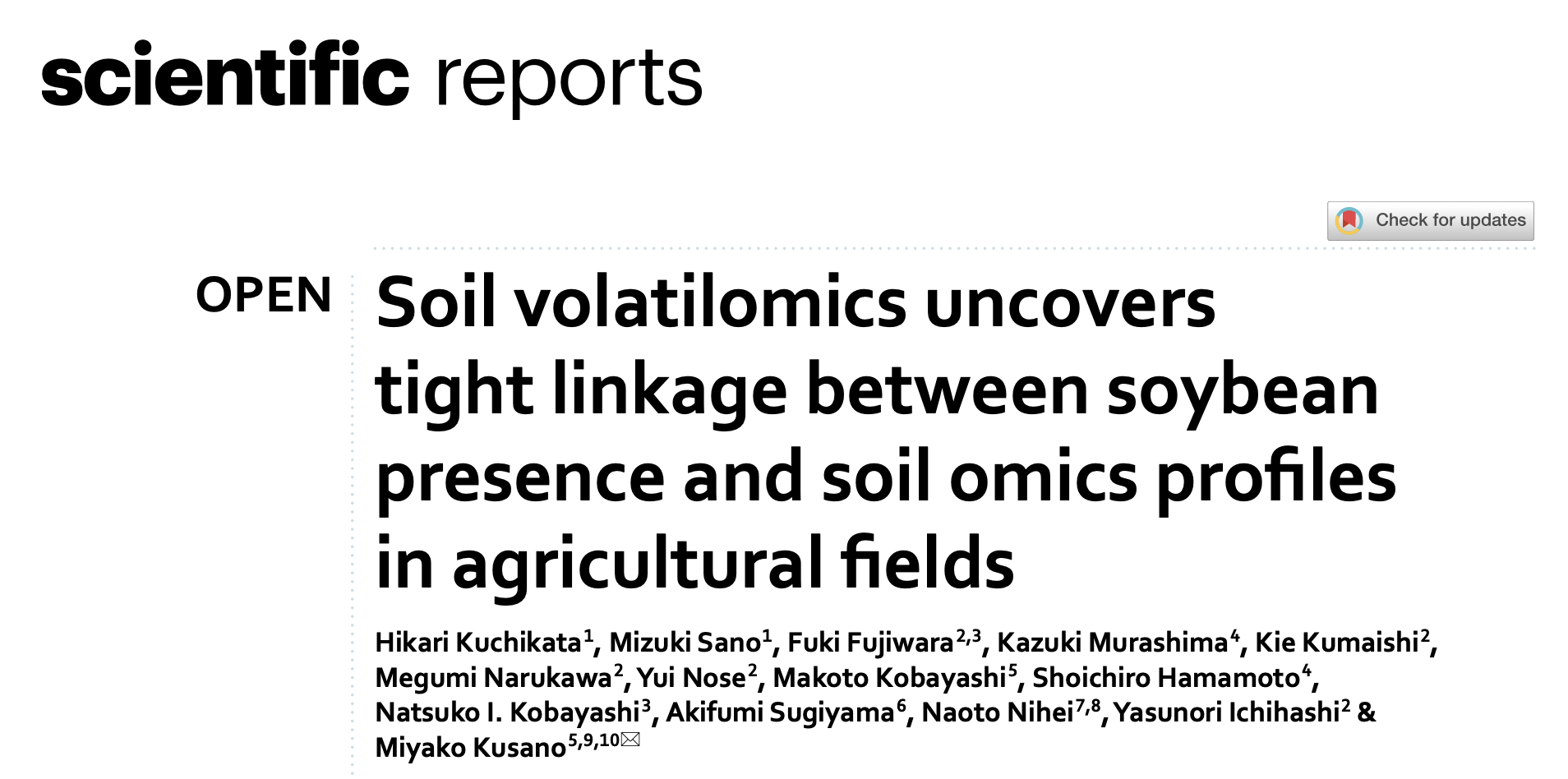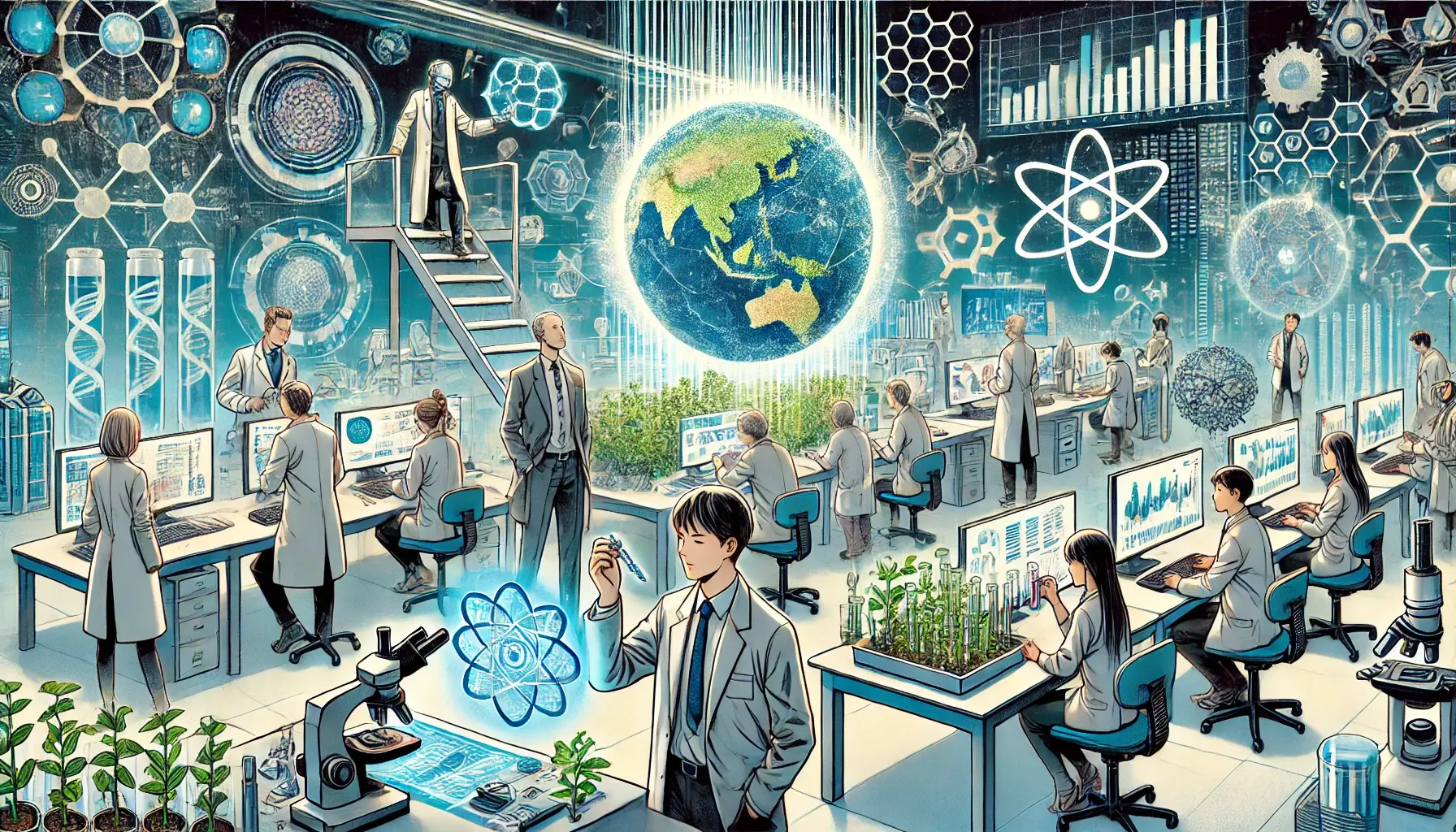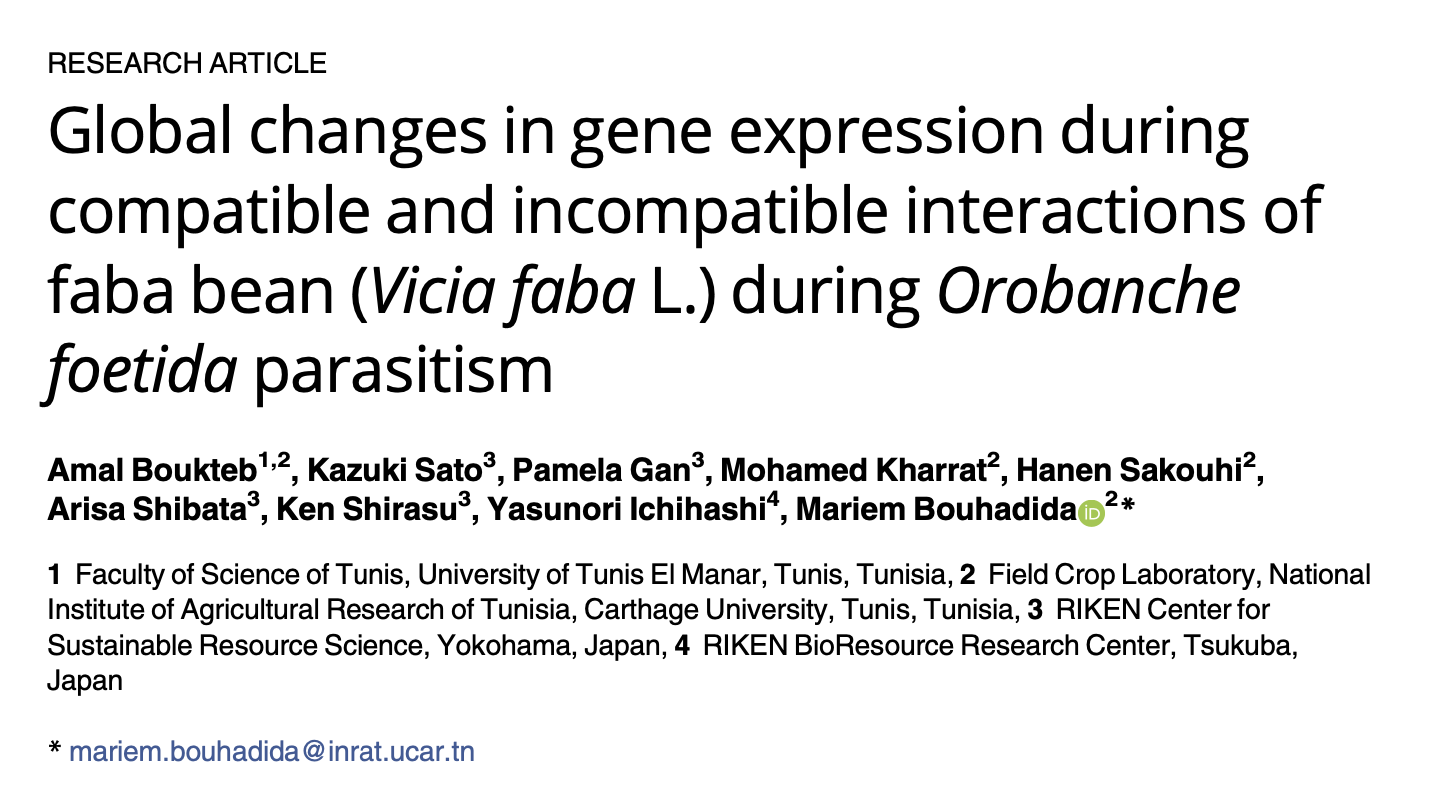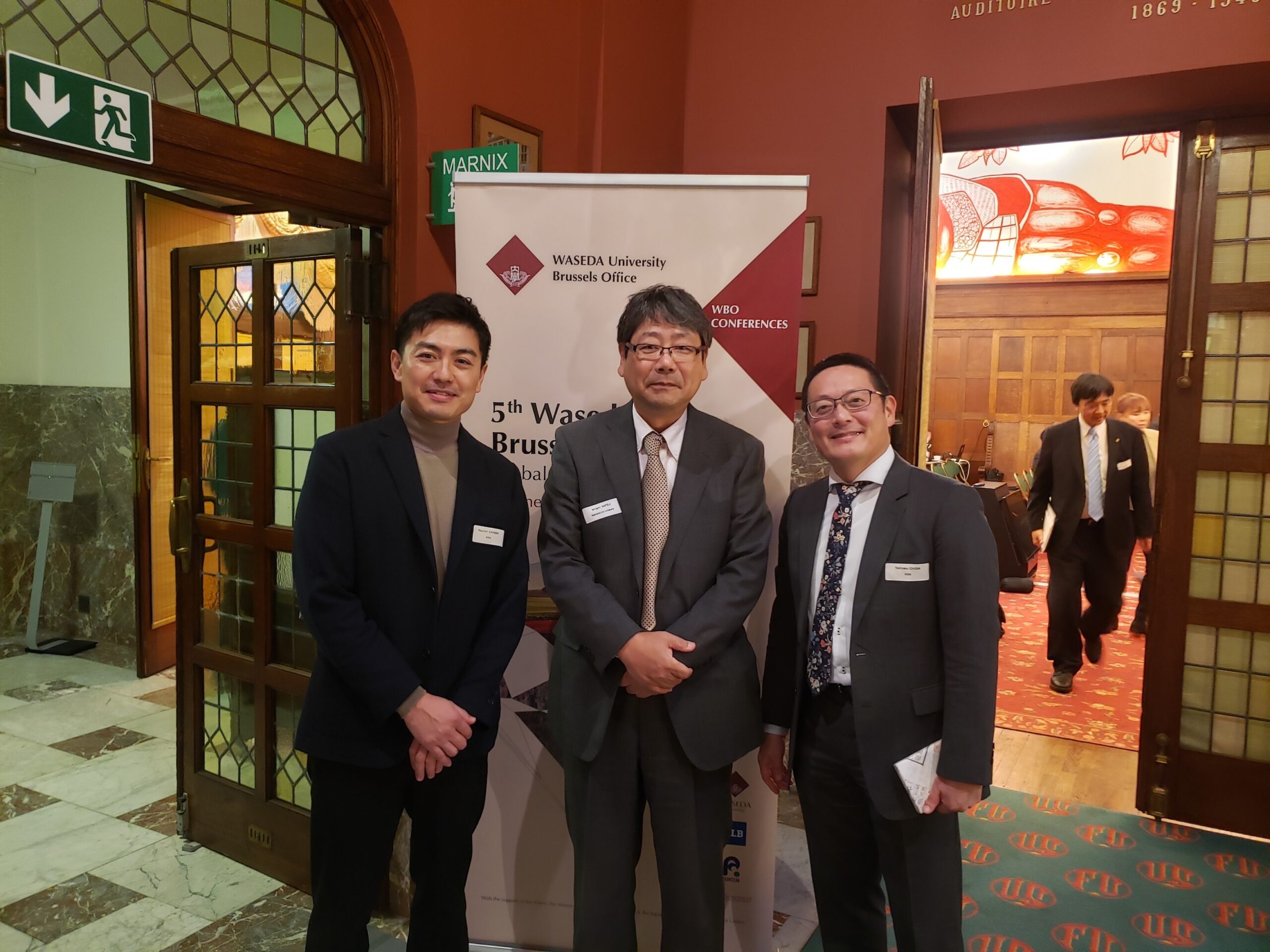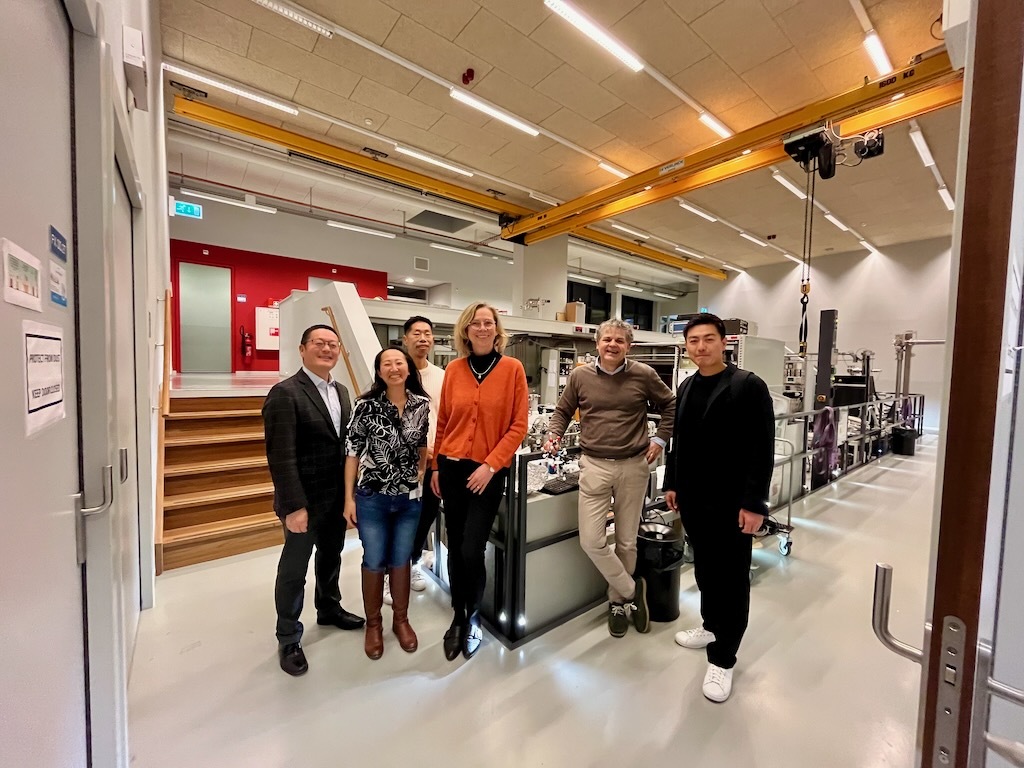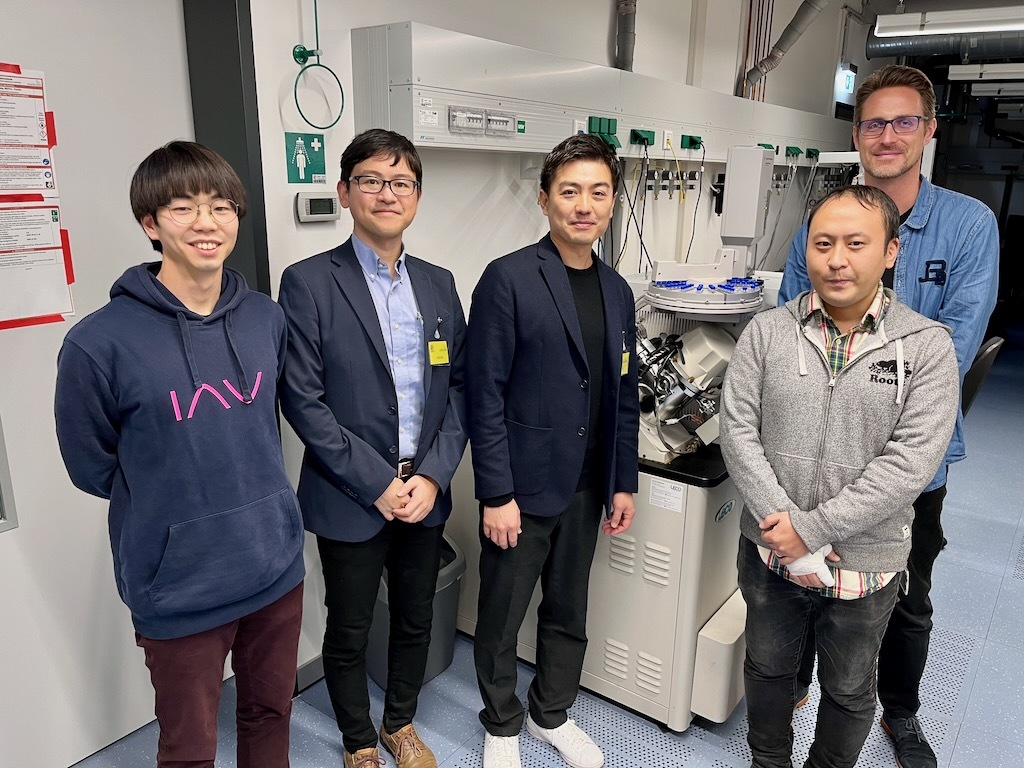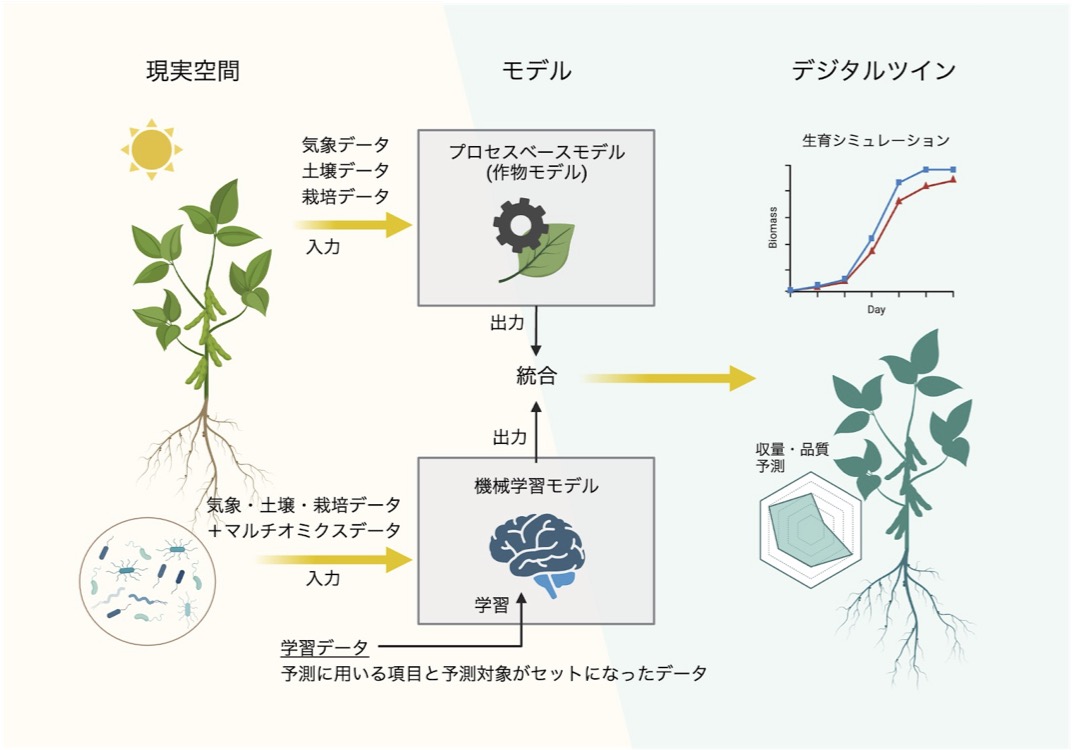今後20~30年頃まで先を見通した学術振興の「グランドビジョン」を示すため、日本学術会議により「未来の学術振興構想(2023年版)」が策定されました。私も中長期研究戦略 No.22「顧みられない未利用種(NUS)の遺伝的改良に基づく持続可能なagro-ecosystemの確立」の作成に関与させていただき、非常に貴重な機会となりました。
提言「未来の学術振興構想(2023年版)」:
https://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kenkyukeikaku/kousou23.html
そこで、ここで提案されているグランドビジョンについて考えることで、自身の研究を少し離れた位置で俯瞰的に捉えて、冷静に自身の研究の未来を見つめる良い機会になるのではと思いました。私たちの研究分野は、グランドビジョン4「地球の生命環境と食料供給を持続させるための学術創生」に関係します。今回はこのグランドビジョン4を読んで、私が考えたことについて書いておきたいと思います。
グランドビジョン4には、6つの中長期研究戦略がありました。これらに共通してみられる考えを象徴するキーワードとして、「サステナビリティ」、「調和」、「ワンヘルス」、「IT」、「分野横断」、「階層を超える」がありました。その背景には、現在の細分化された学術分野が指摘されており、今後は統合の方向へ向かっていくことが文脈から読み取れました。その際に必要な能力として、個別の知識量でなく俯瞰的な視野で先入観のなく解釈する能力が求められるだろうと思いました。
一方で「IT」というキーワードがありながら、大規模データ取得の障壁を超えるアイデアや時空間を超えた発想が少なく、抽象度が高めで具体性が低いという印象を受けました。中手世代から大御所世代が中心となって考案されているため、その具体は次世代の若手に求められていると思います。加えて、突飛なアイデアがありながらも、データサイエンスで注目されている生成AI、web3、量子コンピュータについて言及がされていないことから、本分野でのデータサイエンスの応用がまだまだ限定的であり、将来的に伸び代があるトピックスと捉えることもできるかと思います。
もう少し解像度を上げて考えてみたいと思います。今後20~30年後となると、現在20歳の学生が40歳~50歳になる時代になります。デジタルネイチャーであり、SNSなどでの人的ネットワーク構築に抵抗感が比較的少ない世代が中心の世代になります。また日本を含む多くの先進国では、少子高齢化による人手不足で売り手市場となり、学術研究へ進む人口は圧倒的に低くなることは間違いないと思います。さらにモノからコトへの価値観のシフト、資本主義から知識主義へのパラダイムシフトが生じつつあることを併せると、デジタルと自然が究極的に融合していく姿が想起されます。さらに科学が一部の人々が携わる特殊な営みではなく、社会全体へと浸透する形で組み込まれ、そこから出てくる知識が社会へ直接フィードバックすることが求められていくのではないでしょうか。
科学が追求する真理への到達は果てしない旅路です。このことは当事者である科学者にとって当然のことであるものの、その果てしなさについて想いを馳せることは日常においてほとんど無いかと思います。科学の進展により、その真理への到達の果てしなさが明確化されると、物事の全てが科学で明らかにされるという科学至上主義から異なるイデオロギーへの転換の可能性も考えられます。ひょっとすると、人類が宇宙への生存圏を探索することを諦め、完全に知ることができない深遠なる自然の叡智から人類が必要とする情報のみにアクセスする術を学び、足ることを知るといった社会へと回帰するシナリオも十分ありえるかもしれません。
プラネタリーバウンダリーで象徴されるように、物質レベルで人類の転換期が定義される今、科学自体もまたその転換を迫られているように思います。そのため、今後の数十年は、これまでの数十年の変化よりも、より大きく変化する時代となると考えられます。そもそも未来の学術研究について考えようと試みたのですが、私の想像ができる範囲は余裕で超えることが起きるということを考えるようになってしまいました。そんなことをぼんやりと考えてながら、のらくら農場の萩原さんの著書「野菜も人も畑で育つ」を読んでおり、ハッとする言葉がありました。
“分からないまま進む力”
自身の経験や過去の教訓という物差しでは、なかなか価値を測定できるような時代でないからこそ、自身の嗅覚を信じ、分からない状態でも流れに乗ることが大切になると強く感じました。